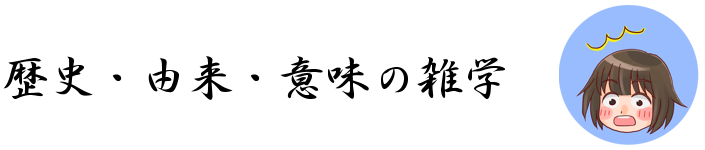周りを顧みずに、必死になっているようなイメージで使われる「がむしゃら」という言葉。

大抵は、「がむしゃらに仕事を頑張った」などのどちらかというと良い意味で使われることのほうが多いように思えます。
これは「がむしゃら」という言葉になじみがあるからこそなのかもしれませんが、がむしゃらにはその音感からも強い意志のようなものを感じますね。
ところで、がむしゃらっていう言葉は何が由来になっているのでしょうか?まさか「ガムシロ」が語源になっているわけではなさそうですが・・・
ということで、がむしゃらの由来、語源、本当の意味や漢字で書くとどうなるのか、などを調べてお伝えしたいと思います。
がむしゃらの意味・由来とは
がむしゃらというのは後先考えずに強引に振る舞うという意味の「がむしゃ」に接尾語「ら」をくっつけた言葉です。
これだけでは由来の説明になっていませんね。つまり「がむしゃ」の由来についても掘り下げなくてはなりません。
がむしゃらというのは、漢字で書くと「我武者羅」です。「羅」は当て字です。
そのままで解釈するなら「我が強いわがままな武者」が由来ということになります。かつては貴族が支配していた世の中において、貴族に変わって台頭したのが武士、つまり武者でしたね。そんな「下剋上」を文字通りやってのけた武者というのは、多少わがままなくらい我の強さがないと出世はできなかったのでしょう。
しかし、江戸時代の文献によると「がむしゃ者」という表現があるようで、もし「がむしゃ」が「我武者」という漢字で書くならばこれは「我武者者」という不自然な形になってしまいます。ということで、そもそもこれは「武者」自体が当て字である可能性が高いようです。
あるいは、我無性(がむしょう)という言葉が転じて我武者羅になったという説もあります。
「無性に~したい」というように、無性という言葉には「我を忘れて」とか「自制心を失って」という意味があり、これもがむしゃらのイメージとしては合っています。
ただ、そうすると「我無性」の頭の「我」という漢字と「我を忘れて」の我が重複してしまうんですよね。日本語にはあまり、意味の連なる言葉を重ねるというものがないのでこれもちょっと違うような気がします。
「危険が危ない」とか「頭痛が痛い」とかいう類の表現と同じですね。
さらには、「我にむしゃくしゃする」からむしゃがついてがむしゃになったという説もあります。
これは由来としてはあまりにストレートすぎて、その音しか見てないというか単純すぎます。そもそも「がむしゃら」って別に自分にむしゃくしゃする、なんて自責の念を感じるような表現とはちょっと違いますよね。
そんな中で「がむしゃら」の由来の最も有力な説として挙げられているのが「我貪(がむさぼり)」が変化していったというものです。
貪るというのは、「飽きることなく欲しがる」とか「際限なくある行為を続ける」という意味があります。がむしゃらのイメージとしてもぴったりです。
また、日本語というのは、本来の言葉からより親しみやすい当て字に変化していったり、より言いやすい言葉へと変わっていったというような由来が多く存在します。なので「がむさぼり」が「がむしゃ」、「がむしゃら」へと変遷していったというのはかなり有力な説でしょう。
がむしゃらと無鉄砲の違いは?
ちなみに、がむしゃらと似たような意味の言葉に「無鉄砲」というものがありますが、その違いは「強引さがあるかどうか」にあります。
がむしゃらは後先考えずに強引に振る舞うという意味で、無鉄砲は単に後先考えずに振る舞うことを意味し、無鉄砲のほうが強引さが少し抜けるイメージです。
確かに、無鉄砲のほうが無表情でとんでもないことをしでかしそうな、静かなイメージがありますからね。
どちらにしても後先考えずに頑張るというような意味で使われることが多いですね。
ただ、「後先考えずに頑張る」という行為はあまり推奨されないですね。「頑張ること」それ自体は非常に喜ばしいことなのですが、後先考えずにやってもあまり意味がないように思えます。
おそらく、がむしゃらに頑張るという行為をそのまましたとしても続かないでしょう。何か新しいことを始めようという時には、ほとんどの人がモチベーションが最高潮なのでその勢いでバーッとやってしまおうと考えるんですね。
しかしいくらやっても結果が伴わないことでモチベーションが低下してしまい結局続かないというのが関の山でしょう。
やはり、きちんと目標を設定してそこに向かって頑張るということのほうが効率が良いように思えるんですね。
まずは大まかな目標を打ち立て、そこに向かって「がむしゃらに頑張る」というのが良いと思います。まあ、目標を立てている時点で「後先考えずに」とは正反対になってしまうので本来の「がむしゃら」とは意味が違ってしまうのかもしれませんが。
あくまでもがむしゃらに頑張るというのは定めた目標の枠内でのことにしましょう、ということですね。